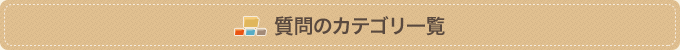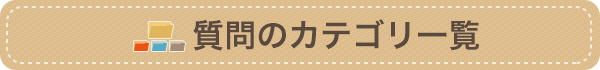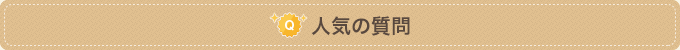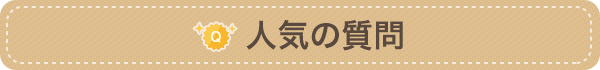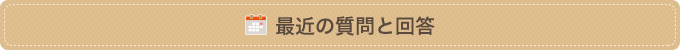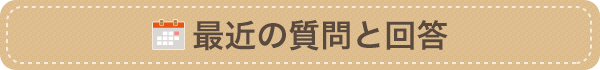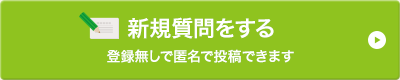孤独死した父の財産や事後の処理について教えてください。
- ミチ
- 2019/12/11
- 葬儀の手続き
20代女性です。
母と離婚した父が、地方で孤独死しました。
警察から連絡があったので、これから父の住んでいた町へ向かいます。
ただし、私の住んでいる土地からは遠く、交通費をねん出するだけで私には精一杯です。
母は父とは縁を断っているので、私が事後処理は行わなけれないけません(そもそも母にも経済的な余裕はありません)。
葬式の費用など出せないので、火葬式で済ませようと思います。
父の銀行口座から、預金を引き出して葬儀費用に充てようと思いますが、問題ないでしょうか。
ちなみに父にはおそらくほとんど財産らしいものはないと思うので(住んでいる場所も賃貸のようです)、相続は放棄するつもりです。
その場合、父の部屋の片づけの費用なども負担しなくて済むでしょうか?
母と離婚した父が、地方で孤独死しました。
警察から連絡があったので、これから父の住んでいた町へ向かいます。
ただし、私の住んでいる土地からは遠く、交通費をねん出するだけで私には精一杯です。
母は父とは縁を断っているので、私が事後処理は行わなけれないけません(そもそも母にも経済的な余裕はありません)。
葬式の費用など出せないので、火葬式で済ませようと思います。
父の銀行口座から、預金を引き出して葬儀費用に充てようと思いますが、問題ないでしょうか。
ちなみに父にはおそらくほとんど財産らしいものはないと思うので(住んでいる場所も賃貸のようです)、相続は放棄するつもりです。
その場合、父の部屋の片づけの費用なども負担しなくて済むでしょうか?
回答は締め切られました
回答2件
弁護士の髙橋と申します。
孤独死したお父様の口座については、暗証番号を知っているのでしょうか。
また、まだ口座が凍結されていない状態なのでしょうか。
基本的に、死亡すれば預金口座は凍結されてしまい、所定の手続きをとらないと引き出せないようになっています。
仮に引き出せたとして、この引き出し行為については注意をしなければいけません。
葬儀費用以上に引き出さないことです。
なぜなら葬儀費用にかかる費用以上に引き出すと、「相続財産の処分」にあたり、相続放棄ができなくなる可能性があります。
相続放棄をした後で、債権者に訴えられてしまうかもしれません。
もし生前の身分等からして、ふさわしい程度の葬儀費用だけを引き出すならば、「相続財産の処分」には当たらないとされています。
葬儀費用とは、具体的には火葬や埋葬費用、遺体や遺骨の回送費用、お通夜の費用、お寺への費用等がこれにあたります。
これらの支出をしても、それが相当な額ならば、相続放棄に影響を与えません。
(ただし、香典返しや墓石墓地の購入、法事費用を「葬儀費用」に入れるかどうかは、金額等によって判断が分かれるので、避けた方が無難です。)
今回は葬式をせずに、火葬式だけということですから、問題はないでしょう。
ただし、交通費は自腹でやるしかありません。
これらの葬儀費用に使用したことの証拠は、必ず残しておきましょう。
もし債権者から訴訟された場合に、反論の証拠として使用することができるからです。
債権者からしたら、引き出された預金が「葬儀費用」に充てられたかどうか分かりません。
もし債権者が「ミチさんが預金を引き出した」という証拠を提出してきたら、「単純承認」(ミチさんが相続を了解した)とみなされる可能性があります。
すると相続放棄は認められず、債務(お父様の借金)をミチさんが全て負う羽目になります。
相続とは、お父様の財産だけでなく、借金も受け継ぐことだからです。
ですから、葬儀費用に使用した金額に関する証拠はしっかり保存しておいてください。
もし相続放棄が完了すれば、お父様の部屋の片づけの費用なども負担しなくて済みます。
それらは不動産業者が業者側の費用で撤去・処分することになるでしょう。
不動産会社から家族に電話がかかってきますが、「相続放棄をする予定」又は、「放棄しました」と答えればOKです。
孤独死したお父様の口座については、暗証番号を知っているのでしょうか。
また、まだ口座が凍結されていない状態なのでしょうか。
基本的に、死亡すれば預金口座は凍結されてしまい、所定の手続きをとらないと引き出せないようになっています。
仮に引き出せたとして、この引き出し行為については注意をしなければいけません。
葬儀費用以上に引き出さないことです。
なぜなら葬儀費用にかかる費用以上に引き出すと、「相続財産の処分」にあたり、相続放棄ができなくなる可能性があります。
相続放棄をした後で、債権者に訴えられてしまうかもしれません。
もし生前の身分等からして、ふさわしい程度の葬儀費用だけを引き出すならば、「相続財産の処分」には当たらないとされています。
葬儀費用とは、具体的には火葬や埋葬費用、遺体や遺骨の回送費用、お通夜の費用、お寺への費用等がこれにあたります。
これらの支出をしても、それが相当な額ならば、相続放棄に影響を与えません。
(ただし、香典返しや墓石墓地の購入、法事費用を「葬儀費用」に入れるかどうかは、金額等によって判断が分かれるので、避けた方が無難です。)
今回は葬式をせずに、火葬式だけということですから、問題はないでしょう。
ただし、交通費は自腹でやるしかありません。
これらの葬儀費用に使用したことの証拠は、必ず残しておきましょう。
もし債権者から訴訟された場合に、反論の証拠として使用することができるからです。
債権者からしたら、引き出された預金が「葬儀費用」に充てられたかどうか分かりません。
もし債権者が「ミチさんが預金を引き出した」という証拠を提出してきたら、「単純承認」(ミチさんが相続を了解した)とみなされる可能性があります。
すると相続放棄は認められず、債務(お父様の借金)をミチさんが全て負う羽目になります。
相続とは、お父様の財産だけでなく、借金も受け継ぐことだからです。
ですから、葬儀費用に使用した金額に関する証拠はしっかり保存しておいてください。
もし相続放棄が完了すれば、お父様の部屋の片づけの費用なども負担しなくて済みます。
それらは不動産業者が業者側の費用で撤去・処分することになるでしょう。
不動産会社から家族に電話がかかってきますが、「相続放棄をする予定」又は、「放棄しました」と答えればOKです。
いろいろご苦労もあり、心情的なもやもやもある中でのお悩みとお察しいたします。
論点を整理させていただくと、①お父様の財産を用いて葬儀等を行うこと、②遺品整理等の費用は負担したくない、の2点と思われますので、順番にご回答差し上げます。
まず、①については、ご自身が相続放棄のご意向をお持ちである以上、残されているお父様の財産を受け取る権利はご自身とは別の「相続人」になります。
つまり、ご自身がお父様の財産を用いるにはご自身が相続人になるしかありません。あるいは、あなたが一時的に費用を立て替えておき、後日相続人からかかった費用を弁済してもらう方法もあります。
②についてですが、これも①のお答えと同じとなります。相続放棄を前提としている以上、お父様の財産から費用を支出することはできないため、あなたが一時的に費用を立て替えておき、後日相続人からかかった費用を弁済してもらう方法をとるしかありません。
仮に、誰も相続人となりえる人がいなかった場合、ご自身へ自治体から相続人となる意向を確認される可能性はあります。その際は、ご自身のお気持ちに従って意向を伝えられるとよいでしょう。
また、ご自身が財産放棄をしつつ、お父様の財産を管理処分する「相続財産管理人」を弁護士等に有料で依頼することは可能です。数十万の費用が掛かるのであまり用いる人もいないのですが、関わりを持ちたくない場合の方法の1つとして考えられます。
もし相続人もなく、遺骨の引き取り手もない場合、居住地の自治体の福祉部局が「無縁骨」として遺骨を引き取ります。ちなみに遺骨は最終的に自治体が提携している寺院等に納骨されるケースが多いようです。
住居の引き払いについては、契約時の保証人などが代行することが一般的です。ご自身が保証人になっていなければ責任を負うことはありません。
また、相続人がいない場合は自治体の福祉部局が財産を確認し、最終的に処分することになります。受け取り手のない財産は民法第959条の定めにより国に納付されることになります。
論点を整理させていただくと、①お父様の財産を用いて葬儀等を行うこと、②遺品整理等の費用は負担したくない、の2点と思われますので、順番にご回答差し上げます。
まず、①については、ご自身が相続放棄のご意向をお持ちである以上、残されているお父様の財産を受け取る権利はご自身とは別の「相続人」になります。
つまり、ご自身がお父様の財産を用いるにはご自身が相続人になるしかありません。あるいは、あなたが一時的に費用を立て替えておき、後日相続人からかかった費用を弁済してもらう方法もあります。
②についてですが、これも①のお答えと同じとなります。相続放棄を前提としている以上、お父様の財産から費用を支出することはできないため、あなたが一時的に費用を立て替えておき、後日相続人からかかった費用を弁済してもらう方法をとるしかありません。
仮に、誰も相続人となりえる人がいなかった場合、ご自身へ自治体から相続人となる意向を確認される可能性はあります。その際は、ご自身のお気持ちに従って意向を伝えられるとよいでしょう。
また、ご自身が財産放棄をしつつ、お父様の財産を管理処分する「相続財産管理人」を弁護士等に有料で依頼することは可能です。数十万の費用が掛かるのであまり用いる人もいないのですが、関わりを持ちたくない場合の方法の1つとして考えられます。
もし相続人もなく、遺骨の引き取り手もない場合、居住地の自治体の福祉部局が「無縁骨」として遺骨を引き取ります。ちなみに遺骨は最終的に自治体が提携している寺院等に納骨されるケースが多いようです。
住居の引き払いについては、契約時の保証人などが代行することが一般的です。ご自身が保証人になっていなければ責任を負うことはありません。
また、相続人がいない場合は自治体の福祉部局が財産を確認し、最終的に処分することになります。受け取り手のない財産は民法第959条の定めにより国に納付されることになります。
墓・埋葬(44)
遺品整理(18)
ペットのお葬式(2)
-
父の位牌と今後の法事などの進め方について -- 先日、父が亡くなり、白木の位牌がうちにあるのですが、位牌を仏壇店にお願いしようとしていてこち...(2021/5/18)
-
母の四十九日に白木のお位牌から過去帳に記載していただきたいです -- 葬儀・お墓・仏壇、エンディング業界勤務歴20年、影山理恵です。ふう様のお...(2021/3/16)
-
母の四十九日に白木のお位牌から過去帳に記載していただきたいです -- ご葬儀お疲れ様でございました。無宗教とのことですが、葬儀は仏式で行った...(2021/3/15)
-
母の四十九日に白木のお位牌から過去帳に記載していただきたいです -- 無宗教ですが 葬儀の際戒名を頂きました過去帳を持っているのですが母もそ...(2021/3/13)
-
戒名料を含むお布施の額が少なかったのではないかと心配‥。 -- 業界歴約20年の葬祭ディレクター小川竜雲と申します。この度のご葬儀、大変お疲れ様...(2020/12/17)
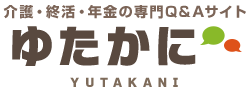
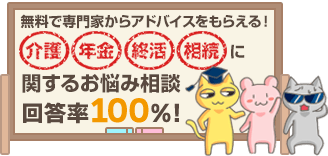
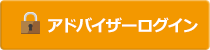
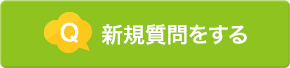




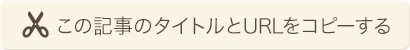

 コメントする
コメントする